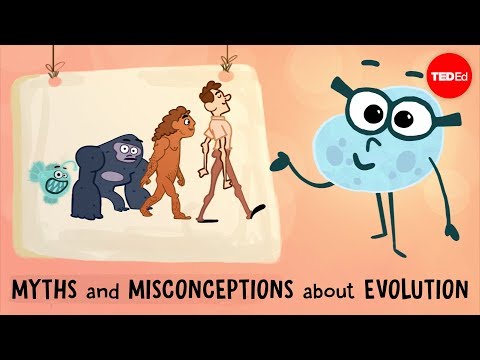
字幕と単語
TED-ED】進化についての神話と誤解 - アレックス・ゲンドラー (【TED-Ed】Myths and misconceptions about evolution - Alex Gendler)
00
VoiceTube が 2021 年 01 月 14 日 に投稿保存
動画の中の単語
individual
US /ˌɪndəˈvɪdʒuəl/
・
UK /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
- n. (c.)個人;個々の項目;個体;個人競技
- adj.個人用の;個人の;個々の;独特の
A2 初級
もっと見る stretch
US /strɛtʃ/
・
UK /stretʃ/
- v.t./i.ストレッチをする : 体を伸ばす;伸ばす : 張る : 広げる
- n.ストレッチ : 体を伸ばすこと;一続きのもの;(一続きの)時間 : 期間
A2 初級TOEIC
もっと見る progress
US /ˈprɑɡˌrɛs, -rəs, ˈproˌɡrɛs/
・
UK /'prəʊɡres/
- v.t./i.前進する;進捗する
- n. (u.)進歩すること;発展;進行
- v.t.促進する
A2 初級TOEIC
もっと見る エネルギーを使用
すべての単語を解除
発音・解説・フィルター機能を解除
