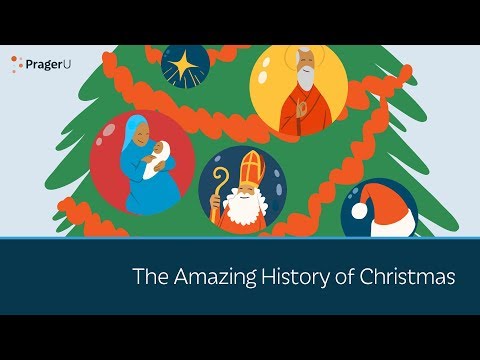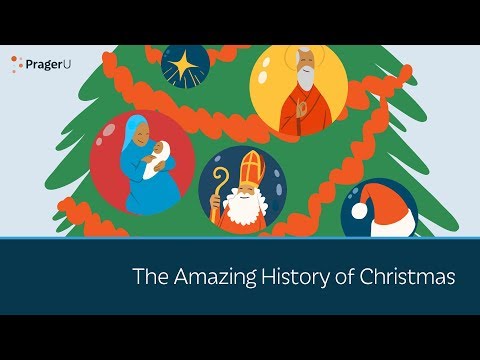クリスマスの驚くべき歴史 (The Amazing History of Christmas)
Amy.Lin が 2021 年 01 月 14 日 に投稿  この条件に一致する単語はありません
この条件に一致する単語はありませんUS /ˌoʊ.vɚˈwɛlmd/
・
UK /ˌəʊ.vəˈwɛlmd/
- v.t.圧倒;圧倒;圧倒;覆う
- adj.圧倒された;圧倒された;打ちのめされた;覆われた
- v.圧倒された;水没した
US /ˈrek.əɡ.naɪz/
・
UK /ˈrek.əɡ.naɪz/
- v.t.(~が本当であると)認める : 受け入れる;(重要性を)認める;法的権威を尊重する;公にその人の貢献を称賛する;認識する、認知する
US /ˈæspɛkt/
・
UK /'æspekt/
- v.i.(ある方向へ)徐々に進む : 向かう
- v.t.世話をする : 面倒を見る
- v.t./i.~する傾向がある
エネルギーを使用
すべての単語を解除
発音・解説・フィルター機能を解除